しゃべり方で出身地がばれてしまうことはよくありますが、地下にコロニーを作って社会生活をするハダカデバネズミでも同じのようです。
ハダカデバネズミは他の個体にそうぐうした時、相手のなきごえのなまりで敵味方を区別している可能性があります。
ハダカデバネズミは社会性を持つネズミの仲間で、毛が無くシワシワの肌が露出している独特の見た目で有名です。
また、老化に抵抗性を持つ長寿の哺乳類としても有名で、研究対象とされてきました。
その社会をしばらく観察してみると、誰でも気づくことがあります。
ネズミたちが、たえず鳴き声を出して「おしゃべり」しているのです。
地下の巣穴には、ネズミたちのチューチュー、ブーブー、キーキー鳴く声が反響しています。

Photo credit: Tim Evanson on VisualHunt / CC BY-SA
科学誌「Science」に掲載された新たな研究によると、これらの鳴き声をコンピューターによって解析した結果、そこに隠れた規則性が発見されました。
ハダカデバネズミは、視力が退化しており、部外者の侵入を嫌う性質があるのですが、コロニーごとの独特のなまりを子供の時期に学習することで、音声で敵味方を区別し、密に協力的なグループを維持できているのようなのです。
社会性を持つ生き物では、言語が重要な役割を果たすのですが、ヒト以外の動物で言語のようなものが確認されているのは、霊長類やイルカやクジラ、鳥類などです。
今回の研究で、その仲間にハダカデバネズミが加わったことになります。
ハダカデバネズミのコロニーは、他の社会性を持つ哺乳類のグループとは異なり、どちらかといえば、アリやシロアリのコロニーに似ています。
コロニーにはそれぞれ一匹の女王がいて、生殖能力はこの女王だけが持っています。
生殖能力を持たない他のネズミたちはワーカーで、巣穴を広げるために地下に穴をほったり、餌となる根塊を探したりして、一生懸命働きます。
餌は貴重であるため、他のコロニーからの侵略者に対しては、しつこく攻撃して追い払います。
研究者たちは、鳴き声についても気づいてはいたのですが、そこに注目した研究はほとんどありませんでした。
強い社会性をもって協力する性質と、頻繁な鳴き声という2つの性質に関連があることは今まで見落とされていたのです。
研究はまずはじめに、7つの研究室のコロニーから2年間に渡って集められた3万の穏やかなチューチューという鳴き声について、機械学習にかけて分析しました。
その解析の結果、それぞれのコロニーには独自の鳴き声が存在することがわかりました。
特に周波数の違いが大きく、一つの鳴き声の間に変化する周波数の数も異なっていました。
ハダカデバネズミ自身もその違いを認識していて、自分のコロニーと同じ鳴き声に対しては返答していましたが、よそのなまりに対しては無視をしていました。
また、聞き覚えのある鳴き声に対して返答しているだけではないこともわかりました。
コロニー特有の特徴を持つ、人工音声に対しても返事をしたからです。
また、これらのなまりが、遺伝的な背景をもったものか、純粋な学習によって得られたものかを知るきっかけを得られたのは、運もありました。
たまたま、同じタイミングで別々の研究室のコロニーで赤ちゃんが生まれたため、3匹の子供を入れ替えて仲間として受け入れられるのかを調べることができたのです。
入れ替わった赤ちゃんは、違う遺伝的背景を持っているので、鳴き声が遺伝子によって決まっているのであれば、敵とみなされて排除されるはずです。
もし、学習によっているのであれば、鳴き声の特徴は新しいコロニーに適応して受け入れられることになるでしょう。
実験の結果、後者が正しいことがわかりました。
鳴き声は学習によってコロニー特有のなまりになっていたのです。
生まれてからの日数が少ないほど、なまりへの適応もつよくなっていました。

Photo credit: herrea on VisualHunt.com / CC BY
また、コロニーごとのなまりは、特有のものですが、固定されているものではありません。
女王が死んで次の女王が決まるまでの、無秩序な時期には、決まったなまりがなくなり、様々なものが出てくることもわかりました。
一度、女王が決まると、コロニーは再び団結します。
女王は他の個体の生殖能力を抑えるだけでなく、鳴き声もコントロールしているのではないかと考えられるのです。
結束力の強いグループなどでは、特有の合言葉やジェスチャーなどで、仲間を見分けたりすることがありますが、ハダカデバネズミも同じ方法で仲間を見分けているようです。
部外者に厳しいハダカデバネズミでは、方言の違いでよそ者同士の会話がもりあがるみたいなことはないでしょうが、「さっき、へんななまりのやつがおった」みたいな会話を仲間内でしてるのかもしれませんね。
参考記事: ScienceNews


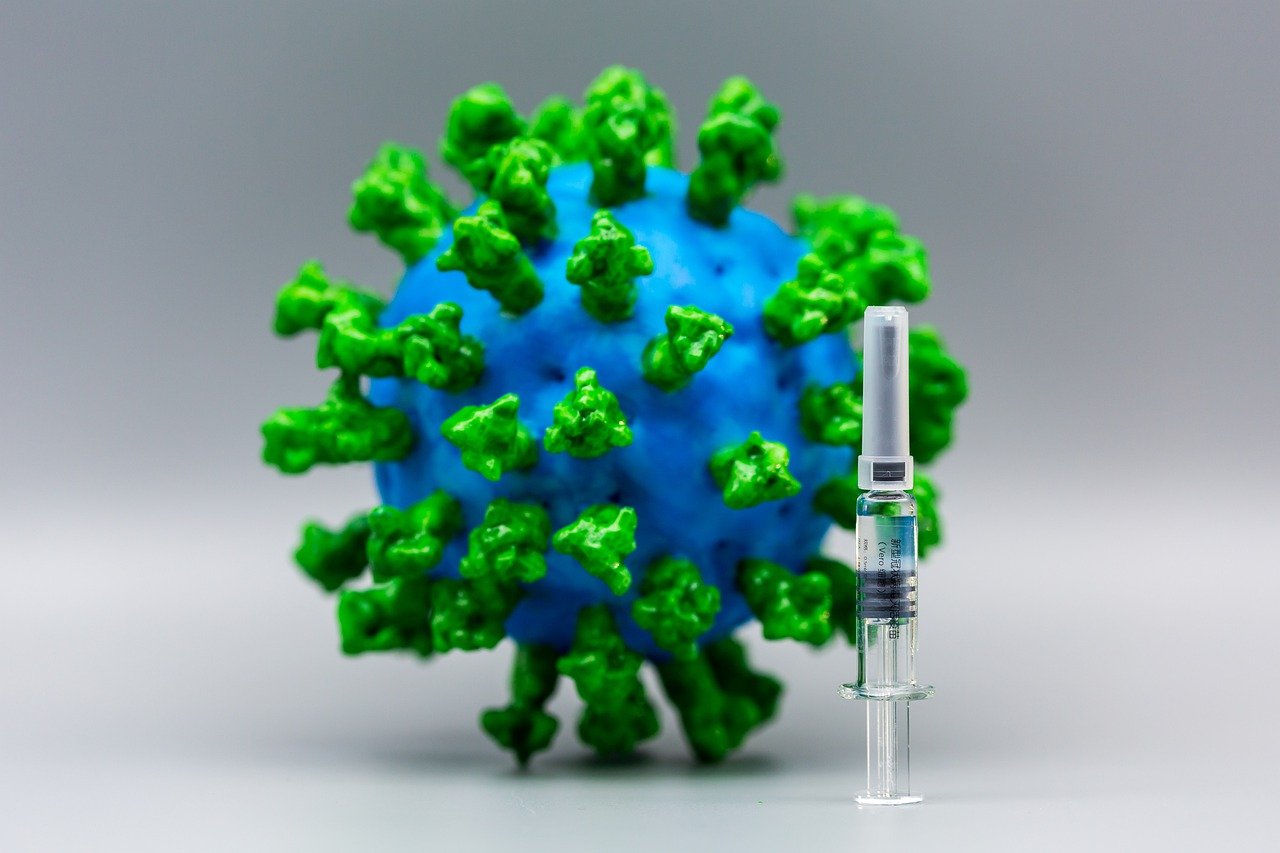

コメント